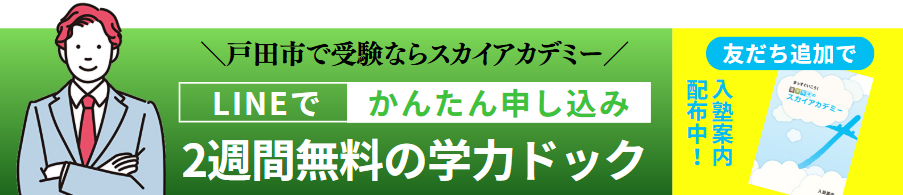こんにちは。戸田市の学習塾・スカイアカデミーです。
高校生にとって大きな分かれ道となる「文理選択」ですが、高校生活だけでなく、大学入試や将来の進路にまで影響します。
今回は保護者の皆さまに向けて、文理選択の時期・決め方・大学受験との関係を整理してお伝えします。
目次
文理選択はいつ行うのか?
高校1年生の夏頃が一般的
多くの高校では、高1のGW明けからアンケートが配られ、夏休み前後の3者面談で文理選択や2年次の選択科目の決定が行われます。理由は、高校2年から履修する科目が大きく分かれるからです。
進級前に方向性を決めなければならないため、この時期が実質的な分岐点になります。
※私立高校など、入学時点から文理が分かれている学校もあります。
※中高一貫校は、中学3年〜高1の早い段階で文理を意識する学校が多いようです。
文系・理系の一般的な区分について
・文系:世界史、日本史、地理、古典などを中心に履修
・理系:物理、化学、生物、数学Bなどを中心に履修
文理の選び方:5つの視点
1. 将来やりたいことから逆算
・弁護士・教師(文系科目)・経営・ジャーナリスト → 文系
・医師・看護師・薬剤師・研究職 → 理系必須
まだ職業が決まっていなくても、「理系でないと入れない学部」が多い点は要注意です。
2. 得意・不得意科目を考慮
・国語や社会が得意 → 文系向き
・数学や理科が得意 → 理系向き
ただし「得意だから」という理由だけで決めると、後悔することもあります。
3. 大学入試の科目を確認
・経済学部 → 数学必須の大学もあれば、社会選択が可能な大学もある
・理系学部 → 小論文や英語を重視する大学もある
早めに志望校、志望学部の入試科目を調べておくことが大切です。
4. 学校や塾での面談
高校の先生や塾の先生は、成績や適性を見ながらアドバイスがもらえます。
保護者を交えた三者面談で方向性を固めるのが一般的です。
5. 実際には「なんとなく」も多い
「友達が理系だから」「国語より数学の方がまだマシだから」といった理由で決める生徒もいます。
だからこそ、保護者や先生が 「将来の可能性を狭めないか」 を一緒に考えてあげることが大切です。
大学入試と科目選択の関係
国公立大学の場合
・文系:英語・国語・数学ⅠA(多くはⅡBも必須)、地歴公民2科目、理科1科目
・理系:英語・国語・数学ⅠA・ⅡB・Ⅲ、理科2科目、社会1科目
👉 高2、高3で「数学Ⅲ」や「物理・化学」を選ばないと、受験できない学部もあります。
私立大学の場合
・文系:英語+国語+社会(日本史・世界史・地理・政経から選択)
・理系:英語+数学+理科(物理・化学・生物などから選択)
👉経済学部のように「数学か社会を選べる」大学もあります。
保護者ができるサポート:声かけの工夫
・将来を考えるきっかけを与える
「もし将来○○になりたいとしたら、どんな勉強が必要か?」
・ 得意・不得意に寄りすぎないよう促す
「数学が得意なのはいいことだけど、それだけで決めていいのかな?」
・ 情報を一緒に調べる
「経済学部って数学が必須の大学もあるみたいだよ、一緒に見てみようか」
・ 迷っているときの後押し
「まだ決めきれなくても大丈夫。選択肢を狭めないように考えていこう」
まとめ
・文理選択は高1の秋〜冬に行われ、大学入試や将来の進路に直結します。
・「将来像」「得意不得意」「入試科目」の3つを軸に考えることが基本となります。
・保護者は“決めつける”のではなく、“選択肢を広げるサポート”をしてあげることが大切です。
スカイアカデミーでは、一人ひとりの目標や適性に合わせた進路相談を行っています。
迷ったときは、ぜひご相談ください!
▶ お問い合わせはこちら